This is 工学 <Engineering.>
Since: Begin of “theGon”
タイトル <for Title.>
公開研究所 <for OpenLaboratory. >
掲示板 <BBS Board 1> <for BBS>
工学 <Engineering.>
寄稿、投稿歓迎! 紹介なども、同様に歓迎しております。 メール又はFTPによるアップロードを使ってください。掲示板も同様。
<Contributions
are welcome. Introduces, too. Write electric mail, or FTP upload. And BBS. >
索引
電子工学研究室 <Electronics
Engineering>
純粋工学研究室 <Philosophical
Engineering >
エンジン研究室 <Engine
research >
エンジン研究室分室 <Branch of
Engine research room >
ロケット研究室 < Rocket research room >
飛行機研究室 <Aircraft
research room>
2輪車研究室 <
2 wheel research room >
乗り物一般研究室 <vehicle research room. >
その他 <Others >
関連リンク <
Links >
電子工学研究室 <
Electronics engineering. >
since: ????
現在準備中。 <Now preparing. >
純粋工学研究室 < Philosophical Engineering. >
入り口はこちらです。<Entrance for Engine res-room here. > 純粋工学研究室
エンジン研究室 < Engine Research room. >
この研究室では、レシプロ(ピストン型)、タービン(ジェット型)、ロケット(型)エンジンについての、数学的な研究を行っています。
<Room for Research for PISTON-CYLINDER type, TURBINE (jet) type, ROCKET type engine. With mathematical>
基本的には、コンピューター上での数理モデル(物理モデル)を主体に研究を行っていこうと考えています。
<Mainly, on computer engine as Physical models and mathematical model.>
模型を用いた、実践的なエンジンの研究もいいかなぁとは、思いますね。
<Somehow, research with METALIC MODEL for practical purpose is good. >
入り口はこちらです。<Entrance for Engine res-room here. > エンジン研究室
エンジン研究室分室 < Branch of Engine research room. >
電気モーター(電気エンジン(原動機))についての研究室です。
<Research room for electric motor.>
モーターの基礎型ならびに、開良案に関する、数理モデル主体の研究を行っていこうと考えています。
<Basic motor and original improved motor research with physical and mathematical modes. >
要望があれば、モーター模型(実際のモーター)作成講座なども開催するつもりです。
<When requested, open lecture of electric motors. >
エンジン研究室分室.入り口。<Entrance for motor-res-room here. > モータ研究室
ロケット研究室 < Rocket research Room. >
ロケット研究室です。
<Research room for Rocket. >
数値解析とモデル解析を主体として研究していこうと考えています。
<Numerical analysis & modeling analysis are main in currently plan. >
ロケット研究室入り口。 <Entrance for Rocket research room. > ロケット研究室
飛行機研究室 < Aircraft research room. >
飛行機の研究室です。
<Research room for Aircraft. >
一般的な重航空機の基礎方程式。・モデルを主体に研究を行っていこうと考えています。
<Popular equation & model of Aircraft maneuver. >
飛行機研究室入り口。 <Entrance
for aircraft research room.> 飛行機研究室
2輪車研究室 < 2 wheel research room. >
2輪車(自転車・オートバイ)の研究室です。
<Research room for 2 wheel. >
一般的な2輪車の基礎方程式。・モデルを主体に研究を行っていこうと考えています。
<Popular equation & model of motorcycle. >
2輪車研究室入り口。 <Entrance for aircraft research room.> 2輪車研究室
乗り物一般研究室 < vehicle research room. >
のりもの一般についての研究室です。
<Vehicle research room >
LGP という言語とゲーム(リアルタイムシュミュレーション)を主体として研究を行なっていこうと考えています。
<With Game (Real-time simulation) by LGP (Computer Language), is plan of this research. >
乗り物一般研究室入り口。 <Entrance for vehicle research room. > 乗り物一般研究室
![]()
その他 <Others>
索引 <Index>
電気自動車のバッテリー交換方式
電気自動車と風力発電を用いた、低運用コストの自動車交通システム
反対熱出力素材
長々波パルス変換型、入力装置
浮かぶレンガ
工学で一般的に用いられている数学に関して 近藤敏郎
ボイラーの改良について <Improving boiler.>
環境エンジンに関して <Circumstance generator.>
工学で一般的に用いられている数学に関して
冷却発電について
アンモニアエンジンに関して <Ammonia Engine.>
合成液体燃料に関して
![]()
論文
![]()
電気自動車のバッテリー交換方式
1/5/2005 10:09:49 PM JMT 近藤敏郎
電気自動車向けの着脱式のバッテリーをスタンドで、充電済みのバッテリーと交換する燃料補給システムを発案したい。
会員登録を基にして、バッテリーに関しては、業務提携済みのスタンドで、交換可能にすると、ほぼ、現在の石油燃料自動車同様の使いかってになりそうである。
加えて、業務容赦の代表であるトラックの電気化も、ここで、提案しておきたい。
(電気自動車のバッテリー交換方式)
電気自動車と風力発電を用いた、低運用コストの自動車交通システム
1/5/2005 8:37:52 PM JMT 近藤敏郎
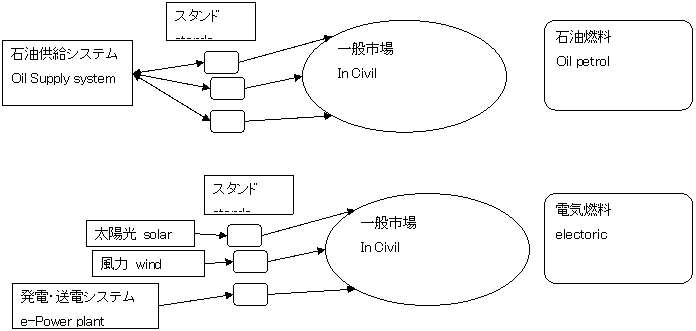
従来型のオイル主体の自動車交通システムには巨大な、石油供給システムが必須であった。
石油の輸送、陸揚げ・保管・「生成」・輸送が、そのシステムの機能となる。
一方、電気燃料の場合には
バッテリーへの充電、が、従来の燃料の補給と重なり、電力の輸送とシステムが重なるため、ランニングコストの低下が期待できる。
又、同様に、風力発電等、スタンドの周辺での環境エネルギー資源が大量に利用できる場合には、この送電システムすら不要で、独立性の高い、補給拠点となるというメリットもある。こちらもやはり、ランニングコストが安く、危険性も少ないというメリットがある。
例えば、海岸線沿いの立地の場合
バージ等を使った、潮汐(ワイヤーアンドアンカー形[1]など)、波力、風力、太陽光、大気・海水型気温差[2]などの、新型の環境エネルギー資源プラント、殆どの利用が可能であり、その規模は、かなりの自由度を持つ。立地条件にもるが、例えば、1ヘクタールを超える面積を占有して、エネルギーの生産が可能であろう。いい加減な数値であるがソーラセル用いた太陽光発電に換算すると、1平方メートル・1時間あたりの太陽光のエネルギー資源を1000Wと考えると、これは、0.5Mワットから、1Mワットに相当する規模である。大体小規模な発電所に相当する出力となる。
実は、初期投資コストのマジックがあるので、例に挙げた数値は実現しがたいのではあるが、可能性と魅力としては否定しがたいものがあるのも事実である。
トータルとしては、電気燃料型に軍配が上がるのではないだろうか?
(電気自動車と風力発電を用いた、低運用コストの自動車交通システム)
反対熱出力素材
10/26/03 11:35:30 PM JMT 近藤敏郎
アイデアというよりも、要望で、応用範囲が広いのにという程度であるが…。
反対熱出力素材
11:32 10/6/03
片側の面を熱する(冷却する)と反対側が反対になるという素材
熱交換などに適した新素材
wanted!
冷蔵庫のメカニズムなどがこれ。
同様に、熱入型方冷蔵庫については、議論済み。
恐らくは、他のメカニズムもありそうである。
(反対熱出力素材)
長々波パルス変換型、入力装置
10/26/03 11:29:19 PM JMT 近藤敏郎
以下、メモのまま
21:25 10/7/03 発案
パルス入力、波長変換
パルスで入力される電波を、波長変換かけて処理する機器。
アンテナが短くなる。
波長にこだわらなくて済む。
ラジオ機器
発信装置も同様。
共同研究者あり。
(長々波パルス変換型、入力装置)
浮かぶレンガ
10/26/03 11:26:42 PM JMT 近藤敏郎
以下、メモのまま
21:31 10/7/03 発案
洋上レンガ構造物
浮かぶレンガを使った、舟などの洋上構造物
オーストラリアのジョン(ニックネームらしい)のアイデア
差し込んでひねるタイプの組み立てレンガ
アメリカ:構造接続型レンガ
(浮かぶレンガ)
工学で一般的に用いられている数学に関して 近藤敏郎
4/11/03 10:10:37 PM JMT
収束と発散という、工学に興味があるあるいは所属している人間にとっては問題である数学関連の問題である。
(工学で一般的に用いられている数学に関して)
![]()
ボイラーの改良について <Improving boiler.>
蒸気機関用のボイラーの改良についての研究です。
ボイラー研究室入り口 <Entrance for boiler research room. > ボイラー研究室
![]()
環境エンジンに関して <Circumstance
generator.>
環境熱エンジンという用語を発語し、はやらせた元兄[3]である筈なのだが、概念を更に広く取るのが望ましいだろうと考える。よって、環境エンジンを従来の環境熱エンジンの用語ならびに概念とおきかえて、欲しい。
この研究の発端は札幌電波管理局BBS TCNのBBSボードのアーティクルから始まるのであるが、「マックスウェルの悪魔」と永久機関の研究を元にしている。一部の論敵は、沖縄の海洋博で既に模型展示されていたという主張をしているが、起源と情報源が異なるのだと改めて主張したい。
既に、この研究は数年の実績を経て、実用化にこぎつけたという未確認の情報が入っているものも含めて、数種(恐らくは、情報が入っていないものまで含めると、10数種から数十種に及ぶであろう。)の異なるアイデアが、存在している。
又、現時点ではこのページと、この研究室が、環境エンジンの発祥の地(既に、順序は逆になっているだろうが)であると、ここにつつましく主張する。
12/29/02 12:51:06 AM JMT
(環境エンジンに関して)
![]()
アンモニアエンジンに関して <Ammonia Engine.>
6/19/03 12:58:40 PM JMT 近藤敏郎
アンモニアエンジン
アンモニア+空気+熱
=窒素、水+エネルギー
古いアイデアの再記述
4/23/03 22:20 JMT 付のメモから
塩素エンジンが最初のアイデアだったと思う。
一般の燃料+酸素という、大気中での酸化反応(年少反応)ではない、科学反応を用いた、内燃機関に関するアイデアのことである。
圧縮空気、液体空気と空気科学(大気科学ともいう)から、例えば、太陽電池・風力で電力を起こして、伝導のコンピュレッサーを稼動、アンモニアを作って、燃料に変える。というサイクルである。
図にすると以下のようになる
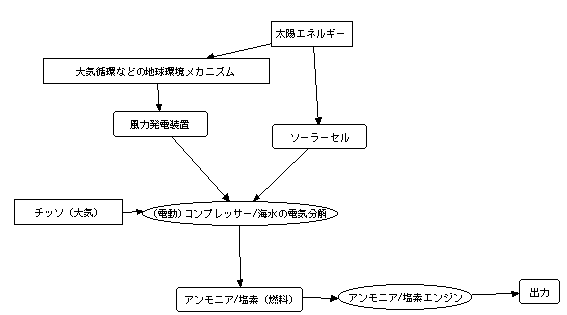
図 1
アンモニア燃料サイクル、塩素燃料サイクルも同様に併記した。
基本的には、アンモニアを酸化・燃焼させて熱エネルギーを取り出し、通常のガソリンなどの代わりにする。というアイデアである。
ちなみに、
アンモニアの燃料サイクルは、
水素の燃焼と、チッソの脱水素反応からなり、窒素と水とエネルギーを生ずる。
○
水に溶かしたアンモニアを液体燃料として(プレヒートしてアンモニアを抽出して使用する)というアイデアもある。
燃料電池の燃料としてのアンモニア、(水酸化アンモニウムとしてのアンモニア水)も、有効であろう。Ph が 11.9 (4.9 med[4]
酸換算で、Ph2.1 )となる。加えてアルカリであることから、容器による保管などの面からは酸よりも扱いやすいという特徴を持つ。
常温では、夏場でもなければ、大気中に立ち込めて、呼吸困難や呼吸障害などを引き起こすのは、狭い範囲であるといえるだろう。大規模な工場などでの事故の場合には、塩素の流出事件などと同じ規模の、人的・環境的被害を生む可能性は、無く習いだろうが。
付記:
オレンジジュースを使った、燃料電池はどうか? のカゲの声あり。ついでに付記しておく。ちなみに、PHは3で、濃塩酸とほぼ同じである。
(アンモニアエンジンに関して“の終り)
![]()
合成液体燃料に関して
6/19/03 1:37:57 PM JMT 近藤敏郎
ソーラーセル・風力発電によって得たエネルギーで、オクタン(所謂ナフサの主成分)を合成する。 というアイデアである。
これに関しては、アメリカ国内で合資ベンチャーが動いている筈なのであるが、今、どうなっているだろうか?
基本アイデアは、生ゴミ、二酸化炭素、+エネルギーから、保存と利用が容易で、工業原材料としても有用であるナフサを生産、一般の石油系流通におろすというものである。
余剰電力分から、ナフサ(アスファルト[5] )を製造し保管するのは、かなり容易であると云えそうである。これに関しては、電圧がはじめから低めの末端送電回線を用いると、余剰電力の算出と観測が容易で、通常の配電にかかる負荷を低くしての、余剰電力の利用がかのうであろうという発案も出ている。[6]
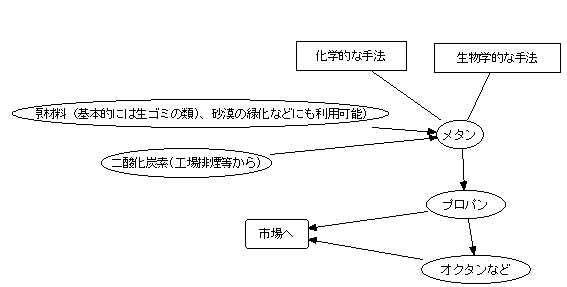
図 2 原材料サイクルについての説明図
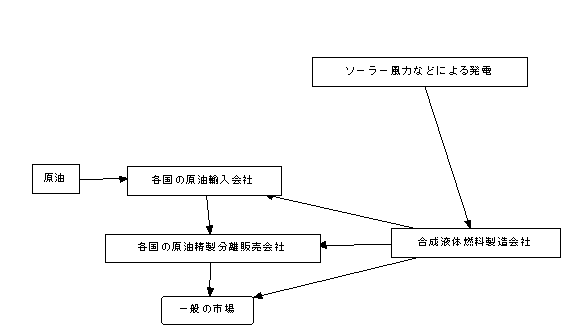
図 3 新規の合成液体燃料の市場(経済構造)との連結構造
ナフサ、アスファルトを共通の通貨として使うというアイデアが、基盤
補足:恐らくは、太陽光が豊富なアラビア地域(現産油国地域)をこの合成液体燃料の主産地(主輸出地域)として開始するのが、国際政治のバランスなどの兼ね合いからは望ましいだろうと考える。
現時点は、もっとも、流通などの社会構造・経済構造に対する負荷あるいは圧が小さくて済む、ソフトエネルギーパスへの切り替え手段と評価できるだろう。
(合成液体燃料に関して)
![]()
関連リンク links
|
|
|
|
||
|
theGon 内 |
In “theGon” |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
||
|
theGon 外 |
Out “theGon” |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
(関連リンク)
![]()
update: 9/30/03 6:42:02 PM JMT: 一部、記述の間違いを訂正。
Updated: 8/23/2004 11:26:18 PM JMT
<End of Contents. >