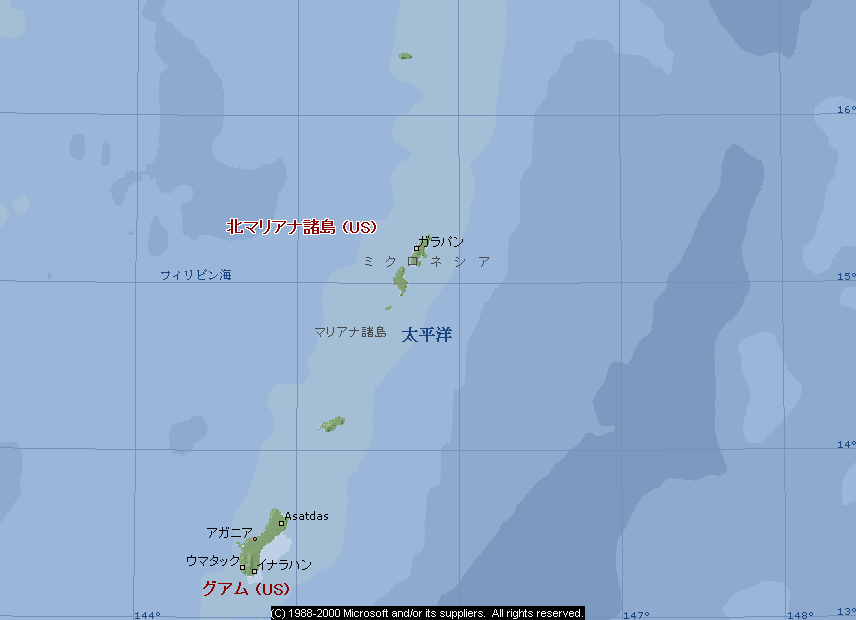This is “Mariana”,”Mariana”
Since:2/24/2005 5:51:58 PM JMT
|
Title |
|
|
HomePage |
|
|
OpenLaboratory
theGon |
|
|
Politics |
|
|
Official
Nation Assistance |
|
|
|
|
|
|
|
|
<for BBS board> |
|
|
|
|
|
Contact with |
マリアナ諸島 開発プラン
Mariana Island
地域交通を整備し、グアム島からの国際航空路を活用した、国際高速貿易によるプランである。
既に、このプランと同様の考えから、テニアン・サイパン島の交通の整備プランが動いている[1]、とのことである。
This plan is 、by international air-way from GUAM
island, for international high-speed trade, by local traffic improvement.
Already, Tinian is.–
|
|
|
マリアナ諸島、中心部地図 |
|
マリアナ諸島 島のリスト |
|
|
|
||
|
名前 |
空港 |
町の規模 |
備考 |
||
|
グアム |
国際空港 |
2万人超、市外区形成 |
最南端 |
||
|
ロタ |
無し |
村落 |
|
||
|
アグリジャン |
無し |
なし |
|
||
|
テニアン |
無し |
村落、複数 |
|
||
|
サイパン |
無し |
5千人規模 |
|
||
|
アナタハン |
無し |
無人? |
|
||
|
サリガン |
無し |
無人? |
|
||
|
ググアン |
無し |
無人? |
|
||
|
アラマガン |
無し |
無人? |
|
||
|
パガン? |
無し |
村落 |
|
||
|
アグリハム |
無し |
無人? |
|
||
|
ウエストアイランド |
無し |
無人? |
|
||
|
ファロン・デ・パハロス |
|
|
最北端 |
||
|
上記のほか、名前のない島がいくつか存在している。 |
|
|
|
||
|
上記のデータは、マイクロソフトエンカルタ百科地図帳、2001 |
|
|
|
||
基本的には、南北に長い、列島を形成していると考えることができる。
このため、以下の基本プランが出てくる
プラン1:
基本航空路の設定。
|
基本航路概念図 Basic flight pan outline. |
緊急連絡用を除き、基本的には、2本のラインで、各島を結ぶプランとなる。
緑のラインと黄色のラインである。
ここで、主体となるのは、グアム島、テニアン島、サイパン島を結ぶ緑のラインであり、島の人口等から輸送量が多いであろうと考えられるラインである。
黄色のラインは、沿線の人口規模と国際空港への接続時間等から、ローカル扱いでも良いと思われるラインである。
緑のラインをBEA-10型で結び、1日6便までの往復運行が可能である。
加えて、各島に1機以上の水上機を配置して、医者などの社会サービスへのアクセスを高速・容易にする。
加えて、無線による情報ラインの整備を行い。
病院船並びに施設船、タンカーなどによる、島の施設の拡張と保全。
サイパン島とパガン島をハブにしたローカル航空路。
マリアナ諸島、列島の長さは、南端のグアム島国際空港から、北端のファロン・デ・パハロスまで、約850キロ、日本列島の半分の長さである。
り発着にかかる時間を含めて、片道フェリー(無着陸飛行)で約2時間(1時間半、そのうち飛行時間は1時間)程度となる。これは、ジャンボジェット並びにB767クラス、亜音速巡航旅客機での数字である。
ローカル航空路で用いられる旅客機の場合には、速度がその半分、時速約500キロ前後であるため、飛行時間が2倍となり、約二時間半の飛行ということになる。
さらに、中古型の民生機クラス(セスナといわれるクラスなどが、これであるし、沖縄周辺でのローカル航空路に用いられている期待もこのクラスである)では、更にその半分の時速200キロであり、飛行時間が更にその2倍となり、約4時間半(内飛行時間は4時間)となる。
問題となるのは、空港であり、これには、中小規模であっても、かなりの経費がかかるのと、サイパン・テニアンを初めとした大き目の島でなければ、良好な立地が難しいという関係がある。
ということから、水上機による、各島への連絡・空路の設定か、バージ型の空港を用いた近海洋上空港の設置、というプランになるだろう。
水上機による空路プランの場合には、燃料タンクの設置と桟橋、並びに関係建物、ターミナルと管制塔などの水上空港関連施設の設置が欲しいところである。燃料タンク、桟橋などはバージを用いると、粗無視できる金額[2] となるし、管制塔並びにターミナル類についても、ほぼ同様である。実質上、燃料輸送ラインの形成と機体整備契約と工場の確保[3] などの手間だけで済む、といえるだろう。
一方、海上空港の場合には、ケーソンを用いた、浮き・準埋め立て型空港の場合には、ケーソン単価で考えると、基本長さ10メートルのコンクリートケーソン(中空、鉄筋補強型)を用いる場合には、幅が40メートル4つ、長さが、1500メートルクラスで、150個、都合600個、単価が2000万円バージ費用がひとつにつき30万円前後と考えて、121、8000万円前後という数字が出てくる。122億円で、日本における陸上での同程度の地方空港の整備費用途同程度、といえる金額であろう。想定金額は少しいい加減であることをまず指摘しておきたい。フィリピンなどからのケーソンの調達も可能ではあろうし、又、短歌的にはもう少し安くなる可能性もある、といえると思う。
水上機の場合には、幹線航路が、まず必要であろうと、考えている。これには、現時点では、唯一の選択肢といえる、ロシア産、ベリエフ製中型ジェット水陸両用機の導入A-10型による、主な島への連絡というプランが出てくる。燃料補給が、途中で可能であるならば、ジャンボ並びに767と同様な亜音速巡航が可能になる。つまりは、幹線航路の所要時間が、半日レベルまで、短くなるということである。これにより、必要航空機と、たとえば後述する生鮮貨物類などの連絡の可能性も、出てくる。
マグロ等の新鮮海産物の国際空港積み出しの可能性は、無視できないものがある。日本市場までの距離と日本からの国際便の乗り入れを考えると、マリアナ諸島沖のマグロを生の新鮮な状態で日本の市場へと出荷することが可能である。年間売り上げは、のんびりペースで、5億円を軽く上回り、このプランで述べている新規ローカル空路の開設費用を、数年で返済できる規模となりうる。
P.S.
同様の発想に基づく会社も、存在しているようである。あるいは、プランニング会社か?
![]()
Begin at: 2/24/2005 7:14:44 PM JMT
(end of contents.)