This is 俳句文庫「」. <Haiku archive “”>
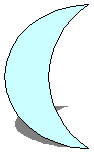 ホームページ <for
homePage “About me.”>
ホームページ <for
homePage “About me.”>
タイトルページ <for
Title Page>
公開研究所 (案内) <for
OpenLaboratory.>
芸術 (案内) <for
Art “Entrance”.>
![]() 文学(案内) <for
Literature “Entrance” >
文学(案内) <for
Literature “Entrance” >
掲示板 <BBS Board 1> <for BBS>
俳句文庫 「」 <Haiku archive “”>
重要 <Important
Notice>
芸術のページで述べたようにこのページに掲載されている作品は、
著作権を放棄していません。
<Again as not in “Art” page, ALL PIECES NOT RENOUNCE COPYRIGHT.>
作品募集中! 言語を問わず
<Wanted!
Any languages! >
索引 <index>
評論 <Criticism for Waka, Haiku, Tanka>
作品 <Pieces of Waka, Haiku, Tanka>
(索引の終わり) <End of Index.>
評論
評論索引 <index>
(評論索引の終わり) <End
of index of criticism. >
和歌・俳句・短歌とはなにか? <”What is Waka, Haiku, Tanka?”>
和歌・俳句・短歌の世界への招待 <”Invitation for Waka, Haiku, Tanka.” >
古典国文歌[1] の始まりについては、記録には残っていない。又、伝承されている伝説にエピソードも無い。
言葉のリズムの面白さから、言葉比べが起き、風雅の心が言葉比べに上乗せされ、美しさ・面白さを競うということが起きたのではないか? (ちなみに、吉本隆明はキライである。)などが、想起される。
いずれにしろ、和歌・短い言葉の連なりという形式を取った、詠、(うた、である)を楽しむ、何人かで集い言葉を楽しむということが起きていたといえる年代については、万葉集の時代(奈良時代、Microsoft/Shougakukan Bookshelf Basic2 より)だと論が一致していると言える。
和歌・俳句のいずれともことなる形式で、「万葉調」といわれる作風が、万葉集の特徴である。
和歌の成立については、平安期であろうといわれている。いずれも、同一の5・7・7というお馴染みの、短歌と同様の形式である。これについては、平安時代の特徴である王族・皇室を中心とした朝廷とその周辺に、新たに加わった人々(平安期の女性たち)の残した記録が多い(王朝文学の時代ということも出来るだろうが)という点もあるだろうが、万葉集に比べると単一の形式に落ち込んでいる、とみることも出来よう。
戦国期からは、和歌の前 をとった俳句(実は、俳句という名称は江戸の中期になってからの名称である。)が次第に隆高し始める。この時代から、このページでは取り上げない、どどいつ(花柳界あたりでの流行りになったのは、実は更に後の時代で、江戸の後期頃、中期やも知れないである。)などの形式での、古典国文歌が成立、流行り始める。
俳句については、お馴染みの松尾芭蕉とその作品が、元禄期(江戸の終わりで、黒船来航の20年ぐらい前の時代である。)頃であり、その前の時代には、談林派が流行し、今も大阪を始めとした関西では生き残っている俳諧師とその流派、が流行していたという時代背景がある。
俳句については、更に現在の今にいたるまでの流れがあるのだが省略する。
俳句の流行に伴って、下火となった和歌が甦ったという時代が来る。明治の終わりから大正期さらには昭和にかけてである(実際には、日清・日露戦争期とその前の時代であるから、明治の中くらい、あるいは明治期からといってもいいのかも知れない)。短歌という和歌と同じ形式をもった、新しい文学形式の成立である。(ヤレヤレ)。
石川啄木という、よく知られた歌人(墓の中で悔しがるかもしれないが)の、和歌という形式からは逸脱しかけた作風を指摘して、とりあえずこの文章は終わりにしよう。
という訳で、ご大層な歴史と、背後を持った文学形式というのが、和歌・短歌・俳句であるのだが……
5・7・7という前と
7・7という後ろ という音節(日本語のひらがな・カタカナ表記においては、音節と文字は一体一に対応する)が和歌である。内容については、実は、問わないと言ってもいいだろう。
前をとった形式が俳句・川柳・狂歌・**という形式である。俳句と川柳の違いは実は無い、あるとすると俳諧として成立した、句の作り方・楽しみ方からの違いといえるだろう。
その他の形式についても、実は、存在していて、面白い形式ならば流行る可能性は十分にある。
意外と、5・7という形式での表現が容易なのは、日本語、殊に書き文字の背後にあるリズムとスタイルの背後にはこの5・7という言葉のリズムが存在している(強い影響をもっている)からである。
俳諧とその形式、並びに他の古典国文歌の楽しみ方については、後で掲載するつもりでは、ある。
みんなで楽しみましょう。結構、簡単で、楽しいですよ。
P.S.
ジングルという英語の新形式文学というのも存在している。アメリカ合衆国で高校を卒業した人間なら、
誰でもこの形式とある程度の経験はもっているという類のものである。芭蕉先生が、歓んでいるやも知れない。
(「和歌・俳句・短歌とは何か」の終わり)
(評論の終わり) <End of Criticism>
作品
俳句 <for Haiku> 俳句作品へ
和歌 <for Waka> 和歌作品へ
短歌 <for Tanka> 短歌作品へ
俳句
平成17年1月3日 月曜日 午後8時13分7秒 JMT
睦月、3日の狂俳句の会
発句
満点の星と見まがう桜かな
元現代俳人 称して某氏
天の川、区別のつかない桜かな
2の句 男性、(称を送ってください。)
夜桜の香りと紛う、桜かな
称して、夜歩き猫氏
葉の方は、しゃんとしてるよ桜だよ。
称して、夜間飛行氏と、その同輩
元の句は、もうすこし違っていました。
月の名残にふる、桜
近藤、友と、
もしかして、かの地フランスで、新形式の文学が誕生するのかも?
コクトーのもっとも短いといわれている詩の指摘あり
下の句もあり、
彼女の回復を待ちたいところである。
後は、連絡待ちである。やんごとなきの、公式のページなどは、おそらく立たないと思うので…
10/15/2004
6:37:14 PM
秋風に、猫の子も人恋し
秋風に、猫の子も人恋しらし
讃句
猫の子も人恋しらし、秋風に
無知
☆
9/27/2004
11:32:34 PM
「濡れ落ち葉」を発句に
紅葉のかすかに香る濡れ落ち葉
紅葉の流れて薫し濡れ落ち葉
焼き芋も 芋焼酎となりにけり
又、7言絶句、5言絶句の1列のみの、中国詩歌もあるねぇと、話題に出ました。
おそらくは、全国で楽しんだ方、記録した方もいると思えるので、掲示板等への書き込み・連絡よろしく。
☆
水面行く船一筋に波残し
天高く右弦の月と夕焼けと
窓霜を震わせ響く遠吠えの
引っ繰り返ったゴミ箱の 点らぬネオンに 五月風吹く
雲一つ 月と流れて 春の宵
ものいえば秋風の頃思われる
建築関係の人間たちとの句会から
(全て他人の句、残念ながら名前を知らないままだったので…
「連絡があると名前を掲載します」)
冬枯れの 木枯し吹くや 缶コーヒー
冬枯れの 懐温める 缶コーヒー
山の上
冬枯れの 木枯し吹くや 独り身に
冬枯れの 風吹き頂
猫の目の
猫の目の 虹に漂う 小判かな (川柳)
猫の目の 光にも似た 世間にも (川柳)
猫の目の 光にも似た 木枯しに
平成十七年一月三日8:12 PM 自室にて
脳裏にめぐる校長の、坂田明にも似た 「川柳だねこりゃ。」
怪鳥にも似た、隣家の叫び声 「協力あり。」
建設の、 にも似た 暑苦しさ 「後が怖いな、これは。」
空高く 秋晴れの頃 思われる。 「今日は この句で終わり。」
いい宵になりそうだ。多謝。
平成十五年十月二十四日 午後3時25分
15:22 10/24/03
ひっくり返ったゴミ箱の、
路傍の隅の
忘れ物
協力者あり、飲み屋をやっている妹に、捧ぐ
和歌
月詠みの 陰の雲居の 家穏の
花ー輪の
****
****
発句 記録 近藤敏郎
短歌
<End of Contents. >