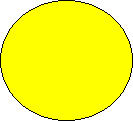This is 商学 <Commercial Science.>
Since :4/5/03 1:57:29 AM JMT
|
|
|
|
<for openLaboratory “theGon”> |
|
|
<for Home page “About me?”> |
|
|
|
|
|
<for BBS.> |
Contact with tkondo001@hotmail.com
商学 <Commercial Science >
掲載論文募集中! <Wanted
articles! >
|
|
商学関連の研究室です 。以前からのアドバイスとして、発言していた、あるいは思いついた経営上のコツや、テクニックなどが、主体となりそうです。
又、掲示板2種を開設しましたのでご利用ください (イタヅラ厳禁! )。
索引
![]()
論文
|
Article |
雑談 |
Talks |
アーカイブ |
Archive |
経営支援 |
Consultant |
貿易経営学
|
Trade administration |
貿易経済学 直接リンク |
Direct link |
|
|
|
経済学
|
Economics |
|
|
|
手形交換情報報掲示板
|
http://6804.teacup.com/tkondo001/bbs |
商品取引情報掲示板
|
http://6804.teacup.com/tkondo/bbs |
|
|
|
(索引)
![]()
雑談
索引
企業の社会的責任について
事業と会社について
(索引)
企業の社会的責任について
10/7/03 8:24:52 AM JMT 再掲載。オリジナルは、92年7月24日の日付。TCN札幌に、アップロード。 近藤敏郎
企業の社会的責任について
タイトルに挙げた文章を読んで、嫌な気分か攻撃的な気分に陥った人も多分にいると思われる。多分、そのような人が脳裏に抱いたイメージは、主婦を中心とする市民運動団体という名の暴徒の群が口々にスローガンを叫びながら破壊的な行動を行なっている、あるいはスーパー等の小売店の店頭でつり上がった目をして製品の悪口を言っている、というようなものだったのではないだろうか?
市民運動の是非は、ここでは言わない。と、いうのは、例え、目的や動機が良いものだとしても程度を越えてしまえば、そして、自分達の行動が正しいものだと思っている人々の愚行や実体を無くしてしまった市民運動というのは、歴史を振り返るまでもなく、存在することは確かであろうし、逆に市民運動が無ければ致命的とまでは言わないまでも将来に渡って悪い影響が残ったであろう事柄もどうように確かであろうから、である。
と、言う訳で、この文章が特定の企業の責任を追及する為のものでも、市民運動に連動したものでもないことは、ここに明かにしておきたい。
僕自身は「経営者」や「資本家」(別に、僕はマルキストではない。と、同時に赤狩りの旗手でもない。)と呼ばれる立場にたったことはない。ただ、市井のゲタばきの1人の生活者として、企業にこうあって欲しいという希望を23述べたい、というだけである。実際に、社会人として生計を立てる手段として企業の一部として活動することは、当然ではあるが、ここではここから少しの間離れることになるだろう。
企業の社会的な責任というコトを考える場合には、まず第一に現在の自由主義経済というモノの根底となている、ある人物の言葉(この言葉は中学生が学ぶの世界の歴史の本にも、必ず出現する、筈である。)を振り返ってみることから始めるたい。それは、アダム・スミスの「神の見えざる手」という言葉である。それぞれの人間の自分の利益を追及するという行動が、全体として見た場合バランスを取り、もっとも望ましい方向へと進ませる源動力となるという、意味で用いられていると、中学校の恩師から教えを賜った記憶がある。同時に習った言葉には、市場機構という言葉と価格の下方硬直性という言葉があったように記憶している。
供給が少なく価格が高いものを安価で市場に供給すると、供給者に利益が上がる、と同時に価格が高く需要が満たされていない市場の価格が下がり需要が満たされる。と、いうのが骨子であろう。
逆に考えると、経済面での企業の果たすべき責任は、市場(国民)の需要を安価に満たす、ことが第一義ということが言えるのではないだろうか? もっともこれは自由主義経済体制というものの中でなくとも通用しそうな考えではあろう、と単純な僕などは思うのだが。
この線に沿って更に考えていった、僕なりの考えというのを以下に箇条書にしてみる。ちなみに、想定したのは製造・流通であるが、これはサービス業の場合も同様であろうと思う。
1)市場の要求に答えること
これは以下の事柄に分類出来ると思う。
a)良い品質
b)安価
c)大量供給
d)安定供給
2)雇用・福利厚生
これは同様に以下の事柄に分類できると思う。
a)法人税・給与等で利益を社会に還元すること
b)労働環境・福利施設の利用機会等
3)公害の抑止
これには、様々な形態が考えられるので一概に「これっ」というようには特定できない。
多分にこれは、僕の考えたものであり、異なる意見をもつ方、経営者の方々及び市民運動に関わる方々等から、「甘いこと言ってるんじゃないよ。」などと言われそうなのは、予期してはいる。
アメリカのフォードさんが歴史的なT型フォードで工場の労働者にも買える価格の車を大量に安定的に供給することから始まった(と、僕は思っているのだが、自動車の歴史研究をなさっている方々から見たら明白な間違いかも知れない。)現在の車社会に対して、2酸化炭素の増大を招いたとか交通事故の犠牲者の数は全世界的に見たなら二つの世界大戦を上回る犠牲者を作り出すことになったとか、その他の理由から批判的な立場に立たれる方々もいらっしゃることは、同様に予期できるし、ロサンジェルスの地下鉄・重金属公害・大気汚染等、様々な形で巨大企業・産業界の圧力等による弊害も決して無視できるものではないとは思うが、生活の隅々にまで浸透し様々な形で我々の生活を支えている自動車の存在を悪く思う方はいらっしゃらないと思う。
全ては、様々な企業の自助努力に支えられた結果ではあろう。
もっともっと、単純に考えた場合、市場(国民)は王様で企業が従僕と考えたとき、どの様な要求であれ、それを満足させるのが従僕としての義務であろう。要求を満足させようと動く過程で従僕が良くない行動が行なわれるのであるなら、良くない行動は取らないように、取らざるを得ないのであるなら自分の要求を見直すというのが良き王様の条件であろうような気がする。自分の欲望に従い他人に犠牲を強いて良いのは赤ん坊だけだと、僕は考える。
従僕がいなくなれば困るのは王様である。従僕が要求を満足出来なくなれば、困るのは、また、王様である。
勿論、僕のおとぎ話を現実に当てはめてみるなら、従僕である企業が社会全体を一般の国民と同じ目で見つめ、善悪の判断を失うことは、そのまま企業としての倫理を失い自己の利益のみを追及することにのみ因われれば、暴力団と呼ばれている非合法の手段により営利を追及する人達との区別を無くすことになるだろうが。
利益の社会への還元については、僕などがあーだこーだ言う必要もないだろう。実際の運用はどうであれ、社員への福利厚生が良くない企業は求職者、及び社員の目にはどの様に映っているかは経営者と呼ばれる人々にとっては大きな問題であろうから。
公害の抑止という点でも、同様のことが言えるだろう。現在の反公害意識の高まりによって、市場に対する影響・法律による取締りその他の面からかなり厳しい基準をクリアすることが要求されているように僕には思えるから、だ。もっとも、見えている部分のみをキレイにしているのでは? という穿った考え方も出来るのではあるが...何れにしろ、公害の規制というのがこれから将来に渡って厳しくなることはあっても規制が緩むことはないであろうから、設備への投資・設備の更新などの機会に出来得る限りの防止対策を考え、実施しているであろうことは、減価償却の点や規制が厳しくなる度に設備を更新することよりは利益面で有利であろうから、想像に難くない。
後ろの二つについては、「当り前」というレベルがかなり高くなって行く(いる)のではないだろうか? 勿論、どんな場合にでも「例外」というのは存在するだろうし、単にそれだけの余裕・知識が無いというのもまた、存在するだろうが。
企業の社会的責任というものについて、僕なりの考えというのを述べてきた訳ではあるが、あちこちから石を投げられそうで、若干、恐い、ので二言三言言い訳めいたことを付け加えて、おきたい。
我々の生活というのは複雑さの度合を増しているし、これからもその傾向は続くだろう。寿し屋に行っても、蕎麦屋にいっても輸入品を目にしないことはない。と、いうことは我々が意識しない段階で様々な国の様々な人々の手を経たものを我々は日常意識しないで口にしているということになるだろう。これはただ単に食品だけではなく、衣食住及びに日常生活で目に触れるもの全てにおいても同様であろう。
と、いうことは、言い替えるならば我々の生活は直接的な接触は無いものの、多くの人間によって支えられていると言えるだろう。そして、それらの全ての人々がボランティアによってそのような行動を取ってくれている訳ではない、ということも。我々が何かを買うということは、目の前にいる店員が所属する商店に金を払うだけではなく、その製品を作る原料を作った人々・その製品を作る部品を作った人々・その製品を作った人々・商店に至るまで運んだ人々にも金を払うことに等しい。同様に、所得を得るために働くという一見、自己本意な目的の為の行為は、所得を得るのみならず・社会の為の行為という側面ももっている。
以上のように個人の社会的な責任が、様々な側面をもっているように企業の社会的な責任というものも考えられるべきではないだろうか?
(企業の社会的責任について)
事業と会社について
7/19/03 10:29:39 PM JMT 近藤敏郎
これは、経済関連の御伽噺の一つである。キチンと理解するといい夢を見ることができるたぐいの話、という意味である。
0. はじめに
(ア) 昔々、あなたとあなたの友人が、大学生だった時。あなたの友人が、コンピュータ関連の新発明をした、特許申請はしたが、未だ世間には公表されていない。数年の間、すごい売上が期待できる新製品を作ることが出来そうである。
(イ) 当然、あなたは、この発明を元にした新製品で一儲けすることを考えた。
1. 資本の準備
(ア) 親に話をして、新会社の設立準備の資金を出してもらうことにした。友人も同様で、会社の設立には不足だが、結構な金額が集まった。
(イ) 二人は、銀行からお金を借りることにした。銀行は、その発明がどのようなもので、どの程度の売上が期待できるのか、知りたがった。
(ウ) 銀行が貸してくれるお金では、会社の設立には不足だったので、あなたとあなたの友人は、株式会社として、新会社を設立することにした。つまりは、大学の門の脇に立って、通る同じ大学に通う、『友人達』に、「株主にならないか? 1と株いくらで株式を買えるよ! 」と、新会社の株を売ることにしたのであった。
2. 会社の設立
(ア) 幸いなことに、株式は、適当な規模ではけ、製造ラインと若干の広告、取り扱い小売店を見つけるまでの運転資金程度には、お金は集まったのであった。
(イ) 株主と、あなたと友人、並びに銀行の担当者は、ある一室に集まり、会社の運営をどうするのか、第1回株主総会を開くこととなった。
(ウ) [1] という、訳で、工場と、製品の積み出しを行うカーポート、とはいっても小さな、家と庭であるがを借り手、電話を引き、2人と銀行以外の最大株主である女の子を事務員(専務)として雇う、という形態で、営業をはじめることが決まった。
3. 営業
(ア) 仕入れは、町の電気屋で、安売りされている電子部品を大量に仕入れることにし、町の電気屋では入手が難しい特許に関する一部の部品の入手は製造元に直接に仕入れることになった。
(イ) 仕入れもとの町の電気屋に、製品を仕入れるように、交渉したが、新製品の斬新さを理解されず、製品の売り先は不明のままとなった。
4. 決算・経理
(ア) 起業のゴタゴタの1ヶ月が過ぎ、重役会議が開かれた。
(イ) [2] 経理をまとめた結果、元金に食い込む損失が出ているという結論だった。
(ウ) 結局、女の子は、会社を辞め、会社への出資者という立場となった。
(エ) 新規に、パッケージのデザインを改め、新規に事務役の女の子を時給で雇い、営業を続けることとなった。
5. 再び営業
(ア) 新パッケージが利いたのか幾分かのまとまった商品の引き取り手を見つけることが出来た。
(イ) 最初の商品の取引先の後、幾つか小さな取引先を見つけることが出来た。
(ウ) 幾分かの小さなブームの後、しばらくの沈黙期が訪れた。
(エ) 町の電気屋で、会社の商品と似た、巧妙に特許にかからないように考案された商品が、あちこちで見受けられるようになった。後、会社への注文の電話が鳴るようになった。
(オ) 営業は、順調で、このまま行くと、初期の借り入れを返して若干の利益を出すことが出来そうだという、経理からの結論も出るようになった。
6. 株主・重役会議
(ア) 会社創立から1年が過ぎた。借りた金に利息をつけて、返済が可能な金額の売上が、溜まった。又、二人にとっては数年の余裕を意味する利益が残りそうである。製品の売れ行きは、ぼちぼちと言うところである。取り敢えずのランニングコストを上回る売上程度である。
(イ) 二人は、それぞれの親と、金を借りた人間を集めて、株主会議を行なうことにした。会社を倒産させて、現時点での利益を、分配する為に。
(ウ) 会社を存続したら、という意見も出たが、会社を特許の販売先を探すこととして、現時点での利益を分配する形での、倒産に、結局は話は決まった。
(エ) 出資者のそれぞれには、利息付で返済を行い。利益の幾分かを出資に応じた比率で分配することとなった。
7. 倒産
(ア) 株主・重役会議の決定に基づいて、二人は会社のオフィスを引き払い、什器備品類の契約を解消し、買い取っていた備品類を販売に出し、会社資産の処分を行った。計画よりも、少し大目の金額が手元に残ることになった。特許のほうは買い手が付かないまま、となった。
(イ) 株主・重役会議の決定どうりに、出資者のそれぞれには、利息付で返済を行い。利益の幾分かを出資に応じた比率で分配した。
(ウ) 二人の手元には、若干の金と、未だ、売れ先が決まっていない特許とが残った。
8. さて、次に…
(ア) 出資者の多くは、次の仕事に関しても、好意的で、「新会社を設立・運用する際には、一声かけてくれ」と、いう態度だった。
(イ) 二人の手元には、若干の金と、未だ、売れ先が決まっていない特許とが残った。
(ウ) とりあえずの休暇をとることにして、二人は、別々に、ちょっとした旅行に出ることにした。
(エ) さて? このあとの二人は?
と、言う訳で、どこかで聞いたことのあるような二人が、会社を始めて、倒産させ、ちょっとした財産を築くまでの、ファンタジーでした。
以上の話には、会社経営に必要な要素がいくつもちりばめられています。
もしかしたら、会社を倒産させて、ちょっとしたお金に買えること、などもかも知れませんね?
(事業と会社について)
![]()
論文
索引
貿易経営学 < trade Administration >
損益分岐点について
手形決済のお助け処置1
(索引)
貿易経営学 < trade Administration >
2/3/04 12:28:13 AM JMT 近藤敏郎
必要あって、貿易経営学[3]のページを立ち上げます。
< I begin Trade-Administration page for need. >
貿易経営学
(貿易経営学)
損益分岐点について
4/5/03 1:57:12 AM JMT
商業においては、投資と利益の蓄積から、投資分(見込み損益)が利益に代わる時間的な、境界が存在する。これを損益分岐点と呼んでいる。
具体的には次のグラフを参照のこと。
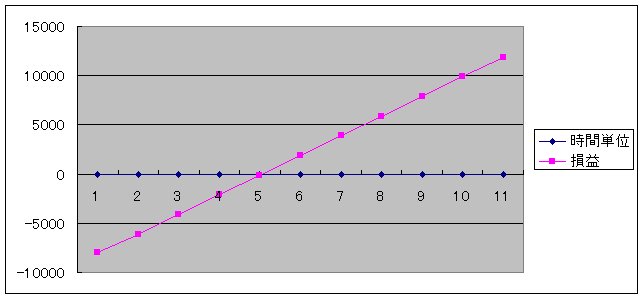
図 1
経営データは以下のとおりである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
時間単位 |
初期投資 |
運用コスト |
利益 |
利益蓄積 |
損益 |
|
|
|
0 |
10000 |
0 |
2000 |
2000 |
-8000 |
|
|
|
1 |
10000 |
100 |
2000 |
4000 |
-6100 |
|
|
|
2 |
10000 |
100 |
2000 |
6000 |
-4100 |
|
|
|
3 |
10000 |
100 |
2000 |
8000 |
-2100 |
|
|
|
4 |
10000 |
100 |
2000 |
10000 |
-100 |
|
|
|
5 |
10000 |
100 |
2000 |
12000 |
1900 |
|
|
|
6 |
10000 |
100 |
2000 |
14000 |
3900 |
|
|
|
7 |
10000 |
100 |
2000 |
16000 |
5900 |
|
|
|
8 |
10000 |
100 |
2000 |
18000 |
7900 |
|
|
|
9 |
10000 |
100 |
2000 |
20000 |
9900 |
|
|
|
10 |
10000 |
100 |
2000 |
22000 |
11900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表 1
この例では、初期投資とランニングコストの総計が、売上の総計を下回る時間単位5が、損益分岐点であると言える。
この損益分岐点の考え方は、かなり重要で、短期計画から、長期計画、単純な経営の分析にも、登場する。
以上、損益分岐点に関して。
(損益分岐点について)
![]()
手形決済のお助け処置1
手形の決済などの場合に、欲しいという要望が多数あるのは、低利息で支払い条件が緩やかな、融資であろう。
従業員の平均的な家計というものを考えてくると、約7万円が貯蓄(いざというときの蓄え分、と家などの頭金予算として)に、まわされているという統計的事実がある。以上から
○ 低金利の融資を受ける
○ 返済計画として、従業員への債権へと切り替える。これについては後ほど、経営改善案をまとめたいと思う。
○ 返済通常どおりに、融資への返済を行う。
金融機関には、従業員の貯蓄分を支払能力の一環(経営的な資源)として、担保化[4] することを勧めたいと思う。 これも又、同様に後ほど別の論文としてまとめたいと、考えている。
以上が、大体の結論であるが、一部、近所にガキが登場し、論文の趣旨とアイデアを食われたような気がしている。文章も、とたんに子供じみた文体へかわり、金融機関関連に母親辺りが、アオシマユキオ[5] を、仕掛けた気配があるし。これから数ヶ月の経済並びに金融関連のニュースが、楽しみではある。 不景気も続き、とんでもない動きを経済を主体とした社会がとっている、という状況にあることだし[6]。
ちなみに
社員給与分を別な形で運用するというアイデアの評価は
平均給与 25万円
内 7万円の比率 28%
給与経費が営業経費の 50%であるという仮説に従うと、このウキになりうる比率は
14%
という計算になる。
という訳で、現在の経費の14%削減を、このアイデアから実現可能ということになる。
薦めとしては、
○ 福利厚生の拡充と、従業員の意識改革から始まった有効利用。
○ 社宅制度と、家賃払いなどから持ち家へと変わる、社員持ち家制度
○ 病気などの場合への、救済社内融資制度
○ 社員債権として、積み立てておく。
後、倒産の際には、債権として優先的に、未払い分を確定しておくことを進めたい。余計な話になって申し訳ない。[7]
などをお勧めしたい。実施的には、社員に損をさせることなく、経営上の経費を削減し、経営状態を大きく改善することが可能になるからである。
(手形決済のお助け処置1)
(論文)
![]()
アーカイブ
|
ファイル名 |
内容 |
フォーマット |
|
月間経費から、年間売上計画、税務掲載を行うシート |
エクセルワークシート |
|
|
|
|
|
(アーカイブ)
掲示板関連のOSL(オンラインソフトウェア)
mamimi オフラインで掲示板を読み書きするツール
ホームページ http://www.geocities.co.jp/Hollywood/5039/index.html
このページからダウンロード
プログラム名 mamimi
バージョン 0.30
対応環境 Windows95以上 (要インターネットエクスプローラ3.02以上)
ソフトの種別 フリーソフト
転載・再配布 自由
著作権者 RatedK <ratedk@geocities.co.jp>
URL http://www.geocities.co.jp/Hollywood/5039/index.html
開発環境 VisualC++ V5.0
特徴
複数のWeb掲示板をURLを指定して一気に巡回し、重いブラウザを開かずに、掲示板をオフラインで読み書きすることができます。
一般的なメールソフトのような見た目&操作感です。
未読の発言をスペースキーのみで読み進むことが出来ます。
MiniBBSをはじめとして様々な形式のWeb掲示板に対応しています。→対応掲示板
書き込みの多い掲示板でも数ページ戻って取得でき、ログを保存できます。
(以上、mamimi について)
(アーカイブ)
経営支援
日銭商売計算
12/29/2004 1:10:42 PM 近藤敏郎
1日あたりの平均客数と1日あたりの平均客単価から、1年の売り上げ計算と、人件費計算を山分けで行うシートを作りました。
エクセルのシートとして、ダウンロードの準備をしています。マクロなどは使用していません。
「開く」で使っても、便利です。
(日銭商売計算)
年間経費計算
6/29/03
8:27:18 PM JMT 近藤敏郎
簡単な月間経費から、年間経費、年間目標売上を計算するシートを作成しました。
エクセルのシートとして、ダウンロードの準備をしています。マクロなどは使用していません。
税務計算も含めています。
「開く」で使っても、便利です。
(年間経費計算)
![]()
history:
updated:7/7/2005 1:30:22 AM JMT mail address changed.
updated: 7/19/03 10:47:25 PM JMT
updated: 10/7/03 8:29:48 AM JMT
This is 商学 <Commercial
Science. >