This is 数学的雑談 <Mathematical talk>
|
<for “Title Page”> |
|
|
<for openLaboratory “theGon”> |
|
|
<for Home page “About me?”> |
|
|
<for BBS.> |
|
|
<for mathematics “Entrance”. |
Contact with tkondo001@white.livedoor.com
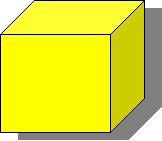 数学的雑談 <Mathematical talk>
数学的雑談 <Mathematical talk>
カオスと乱数の生成アルゴリズム
数学言語の限界と見直しについて
現在の数学の体系と経緯について
宇宙人の数学
(雑談リストの終わり) < End of list.>
数学記号と操作について
9/28/2004 12:21:42 AM JMT 近藤敏郎
数学者[1] ならば、任意の数学的操作を、任意の記号を用いて標記することが可能である。[2]
よって、F という記号が意味していることを特定するのは、実質的に、その文字のみでは不可能である。
これは、又、別のことを意味している。
数学者の自由と、又、その他の[3]
さて、[4]
(数学記号と操作について)
カオスと乱数の生成アルゴリズム
5/1/2004 5:13:56 PM 近藤敏郎
アメリカからの電波である。
JIS企画になっていた、2数掛け合わせ方式による乱数の生成は、ウミユリ型カオス関数を同類ではないかという指摘、である。
危険ではあるが、メモとして、掲載しておく。
P.S.
電波発信元は、きちんと責任とって、論拠と身元を明らかに連絡すること。!
NOTICE
ORIGIN of this telegram must be contact with this site, for responsibility of the ground of argument and ID.
(カオスと乱数の生成アルゴリズム)
宇宙人の数学
6/24/03 2:35:09 PM JMT 近藤敏郎
原アイデアは、1990年代中、数列との問題からである。
「自然数体系を唯一無二の数体系と考えなければならない理由はない。」、定義。
例えば、基底無理数[5] を基準とした数体系であっても特に問題は無い。
ー>1をめぐる、問題は、数体系における得意な関係を意味するだろう。(1を巡る問題)。
『無限小を基底とした、連続数体系を基準とした場合』
現代数学の問題からは、変換の問題と捉えなおすこともできるだろう。
変換の概念を生んだ、奇妙な数体系と自然数体系[6] とを巡る関係に対する疑問といえるのかもしれない。
注釈歓迎!
P.S.
この論文掲載の理由になった人物は、速やかに掲示板・メールにて、論文(小論文、メモ形式のリポートでも可)を送付すること!
(宇宙人の数学)
現在の数学の体系と経緯について
4/4/03 6:06:53 PM JMT
現在の数学の体系と鑑みた場合には、古代の数学体系を、もとに、一部の天才の研究経緯を元にしているといえる。
算数と呼ばれる実用数学の体系(具体的には、数百の例題)と、微分と積分(デカルトの成果である体系)と、それをもとにした研究が、現在の数学の体系の中心であるといえる。
これらを中心となる骨格として、代数学の範疇に入る数式の変形・展開を肉として、数学が発展してきたといえると思う。
現代数学といわれている範疇に関しては、疑問を抱いているというのが、正直な感想である。ことに、アーベルと()から始まったといわれる、数学に関しては、意味が無いのでは? という、気がしている。
(現在の数学の体系と経緯について)
数学言語の限界と見直しについて
<re-recognition and reconstruction of mathematical language. >
いきなり、重いタイトルで失礼。
<Sorry, for heavy title. J>
フォン・ノイマンがやっていなかったコンピュータ・数学的話題を見つけたので、ここに誇らしく掲示します。
<I found a topic which is not already Von Neumann., so I release it. >
もともとの発想は、数年前、数十年前に遡ることが出来るのだが、コンピュータ言語による数学的論理の表示(表記が正しいなJ )が、一般的に云われている数学言語の表記の限界を超えている、ことに気が付いた。
<Origin of this topic is before many years, some ten years before, languages of >
「角谷・コラッツの予想」と云われている(ポピュラーな)問題を、一般数学言語で表記するのは、困難である、というのが証明の代わりであった。
数学言語の代わりに、コンピュータ言語を用いることは出来るが、コンピュータ言語の代わりに数学言語を用いることは出来ない、といのが、決定的であった。
結論としては、静的な記述(スタティック記述)は双方とも出来るが、動的な記述(ダイナミック記述)[7] に関しては、一部、漸化式の様なダイナミックな連想を伴う・動的な記述(トポロジカル(コンピュータ用語)といってもいいだろう)を除けば、数学言語では記述出来ない、という点だろう。
やれやれである。
これに関しては、数学の論文として、コンピュータプログラムにより記述されたものを受ける(数学言語と同様の論理の記述[8] として扱う)べきであるとの意見を提示していたが。
終わり
P.S.
いくつか野心的な論文が世に出ているようである(噂レベルで申し訳ない。)。 後は、情報科学(というよりもプログラミング工学と、学問の進歩、といべきだろう。)から、数学言語としての、コンピュータ言語を認める方向が、出ているらしい(これまた、噂レベルで申し訳ない。)。言語的な制約による、論文と思索の限界を見ていたであろう研究者のことを考えると、喜ばしいと思える。
[本人]
Thursday,
June 06, 2002 JMT J
(数学言語の限界と見直しについて)の終わり)
history:
updated: 6/24/03 2:48:27 PM JMT
updated:5/1/2004 5:18:09 PM JMT
<End of contents. >