This is 地球物理学 <Geophysics>
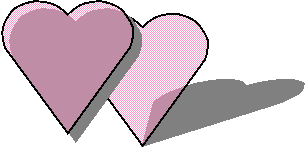
|
<for “Title
Page”> |
|
|
<for openLaboratory
“theGon”> |
|
|
<for Home page “About me?”> |
|
|
<for BBS.> |
Contact with tkondo001@hotmail.com
生物学研究室 <Biology research room>
|
|
掲載論文募集中! <Wanted articles! >
|
|
現在準備中。
<Preparing.>
ガモフ(現代物理学の基礎になっている理論物理学者、故人)のやっていた、DNAの記号・言語的研究の予定です。
G.Gamow,
索引 <Index>
論文 <Articles>
書庫
論文 <Articles>
索引
新種の可能性
スズメの新種報告
生態学 Ecology
種為淘汰
エッセイ 環境汚染についての
発生の問題 7/1/03 1:47:52 PM JMT 近藤敏郎
(索引)
新種の可能性
7/14/2005 11:28:54 AM JMT
写真は無いのであるが、陸地(海岸から400メートル程度、住宅街である)に、移動して定住しているセグロカモメの羽の模様が、陸地へ適応して、というケースを目撃したことがある。羽根の模様については、ほぼセグロカモメそのままで、羽の基本色がスズメ同様の茶色を主体としてた色に変化していた、ケースである。目撃地は、報告者の住所付近、北海道の岩内郡岩内町、字栄、付近、である。
馴化の結果によるものだとすると、陸地へ移動したカモメが大挙して、群れ単位で陸地型へと変化する可能性も、多いと考えられる。
この場合には、おそらくは、世代による継承もやはり同様に起きる、“新種”の発生ということになるのではないだろうか?
もちろん、バッタなどと同様に、住む場所による違いという、分類訳、種の可能性への言及、という扱いも、考えられるのではあるが。
種の可能性と、知られていない能力に関しては、まだまだ、興味と神秘がつきないというところであろう。
以上
(新種の可能性)
スズメの新種報告
6/3/2004 1:38:36 PM JMT 近藤敏郎
最近の観測によると、いわゆるイエスズメ(日本における慣習的な呼び名)
日の丸スズメ:頭頂部に赤い斑点のあるスズメ
日の丸無しスズメ:頭頂部に赤い斑点の無いスズメ
他の部分は、どちらも同じであるように思える。
又、北海道共和町における巣の観測事例からは、0.35ミリの板金覆いを破り、35ミリ角の木材に穴を開け、証明無しの屋根構造を4メートルほど、進んだ屋根の中央部に、稲藁を集めた、直系10センチほどの円形の巣をつくり、糞の跡も残さないで、巣を廃棄した例(共和町田中塗装倉庫、屋根改修工事による)も、ある。
(スズメの新種報告)
生態学 Ecology
10/27/03 1:17:01 AM JMT 近藤敏郎
以下メモのまま、
10:36 7/21/03
エコロジーの結論「生態学」
生き物が生きていくことができるようにする、協力体制(生き物の)
水溜りがあると
空気中の(物を腐らせ、人を病気にすることもある)小さな生き物(細菌、バクテリア)が、活動を開始
水の中の利用可能な成分を元にして、増える
ー>
水の中の生き物が増え、生きていけるものが増える
水の性質が変わり
別の生き物が活動をはじめる。同様に、最初の細菌が動きを止めて、お休み状態になる。
ー>
植物
細菌(極小さな生き物)
空気と水と光から、酸素を出して有毒成分を(一般的には)、水の中の無害な成分に変える。生き物が利用可能な成分に、時として有害な物質を買えて、水、地域の利用できる栄養成分を増やす。
--------
「大抵の生き物にとっては行きやすい環境を作り上げる。』
生き物のリレー、
水の分量とか、質(火山や化学物質())、
メモ以上
以降の生態学の論文は、生態学のページで扱うことにする。 J
(生態学)
種為淘汰
再掲載。93年6月30日 TCN札幌へのアップロード。近藤敏郎
自らの進化の方向を自ら選ぶ種
繁殖のパートーナーの選択の蓄積により、種としての進化の方向性を自ら選択する力が働くのでは無いか?
ー 自然淘汰:適用能力によるふるい分け :一つのサイクル
↓
番い形成:意志によるふるい分け
ー ↓
自然淘汰:環境適応能力によるふるい分け :次のサイクル
↓
ー 選択 :意志によるふるい分け
生き延びた同種の間で、番い形成が行なわれる。番い形成の際に、望ましい形質をもった個体が意図(無意識も含む)的に選択! され種としての特徴の形成が行なわれる。
『鳥は、自らの意志によって鳥に成った。』
「鳥は、環境への適応力によって鳥になったのではなく、鳥に成りたかった種の集合的意識によって鳥になったのだ。」
自然淘汰:環境適応能力(生存競争) :遺伝子の保存
種為淘汰:選択適応能力(繁殖競争) :遺伝子の継承
補注:遺伝子と後天的な学習によるふるい分けという点では二つは全く、同様の効果をある遺伝子の系列に及ぼす。
旧来から言われてきた、自然淘汰への適応を人為的に選択する(番い形成の際の選択)というのは、意義的に見直す必要があるのではないか? 自然淘汰は、例えば捕食されるとか、ある種の病原菌による死、環境による死亡などに限定し、種為淘汰という新しい概念で、番い形成の際の選択を捉えるべきなのではないか?
例えば、雄と雌の特徴が異なる種、雄が雌よりも一般に派手な種の形成の際には雄が派手で目だった方が雌への危険が少ない等の、説明が行なわれて来たが、何故そのような雄の遺伝子が残り、そうでない雄の遺伝子が淘汰されたかについては、番い形成の際の雌の選択によるとの説明以外では、釈然としないものが残る。種為淘汰という概念を導入することで、このような進化をスッキリと説明することが出来るのではないか?
文化人類学に類する事柄
地域により、異性に対する趣向(美的感覚と一般に言われているもの)が異なることが、人種という亜種を形成した、又は価値観の似ている個体同士が集団を形成し、時を経るにつれて価値観、肉体的な特徴、文化とうが、分化し、特徴の形成がなされるにいたったのではないか?
(自らの進化の方向を選ぶ種)
エッセイ 環境汚染についての
10/7/03 8:16:53 AM JMT 再掲載、オリジナルはTCN札幌へアップロード 93年5月中旬。 近藤敏郎
環境汚染についての
某テレビ局のプログラムを拝見していたら、最先端の研究分野での、遺伝子と細胞のメカニズムについての研究というものについて、私にとっては新しい事柄を学ぶことになった。様々な分野で、文字通り日進月歩(もっとも、この言葉自体が既に時代の進歩に取り残された感もなきにしもあらずであるが)しており、自分の考え方というのが必ずしも現実に沿っている訳ではない、あるいは、自分の考え方も同様に、最先端の研究からのフィードバックを受けて変わらななければならなくなるかも知れないという可能性を忘れてはいけないことを自覚させられた。大変に好い意味で勉強になった、と今は考えている。
その中で、一番私にとって衝撃的であったのは、何よりも、細胞の分化のシステムに置ける細胞間での情報のやり取りのメカニズムについてである。q供の頃、学校で生物を教わっていたときから不思議に思っていた1個の細胞が複雑で、膨大な数の細胞からなる器官となり、その器官の複雑且つ有機的に(これは当り前だが)組み上がり生物となり、その結果としての生物がまた、固有の特徴をもち、また、個体差をもつ、その根本的な仕組みが、細胞間での情報となるやり取り! つまりは、神経伝達の仕組みというのが細胞のレベルから成立している! かも知れないと思わせる、研究であった。
単細胞生物なら、単純に自分の複製を作りあげていく、というだけだから、細胞間での情報のやり取りは必要無いわけで、自己の生存を危うくする危険または、餌とする物質を感知するだけで機能としては充分な訳だ。細胞間の情報伝達というメカニズムが必要となるのは、多細胞生物(どんな単純な存在でも! )の成立、つまり各細胞の役割分化というメカニズムを目的とする場合のみ、である。
私のSF的な感覚で考えるなら、この事柄が意味するのは、だた一つの事柄ではなく、各細胞における共通言語(情報の交換を成立させるためには規格が必要となろう。その規格を仮に言語と呼んでおく。)と、方言の存在などの分子言語(これも、また私の造語である。専門家の方々は多分別な観点から、別な呼び名を付けていることだろう。)という概念が考え得るのではないか?、また、細胞レベルにおける自己認識メカニズムというのはどうなっているのだろうか? また、分子言語の成立期・多細胞生物の成立期における歴史! はどうだったのだろうか? とか、進化のメカニズムといのはDNAという細胞内に蓄積されたデータベースと外からの細胞への言語的な刺激という2本立て(多分、今後、このような研究が進むにつれて新たな展開を見せるのではあろうが)によったのではないか? とか、また、環境というのもの生物に与える影響というのを、根底から考え直さなければならないのではないかという危惧、等々の新たなる疑問への扉、である。
そのTVプログラムのその部分を見ていて私が考えたのは、発生段階にある受精卵の分子的な環境(化学・物理学的な環境だが)を変化させると、細胞の分化のメカニズムがそれを感知し、DNAに組み込まれているであろう可変範囲で形成される個体に変異が発生し得るのではないか? という疑問だった。この様な想像が事実である、筈がないが、もし、発生段階(あるいは新陳代謝)における環境がその様な影響力をもつのであるなら、かなり恐ろしくそして輝かしい可能性が目の前に広がっているのではないか? 例えば、ある分子言語を担う分子が豊富にある環境、あるいは低圧低温環境でも、強磁力環境でも構わないが、その様な環境下で繁殖を続けていくなら、細胞の分化の段階においてその環境に沿った変異が強化され、種の分化の様な方向性を育成される生物にもたせることが出来るのではないだろうか? 勿論、1代ではなく、何世代となくその環境下で繁殖を続けることが必要となる(つまりは、DNA対環境という戦いが新陳代謝・細胞の分化というレベルで繰り広げられて行くという図式だ。)だろうが。
東京農大のあの歴史的な兎の耳とコールタールの実験によって癌の発生が確認された様に、あるいはよく知られているように低気圧下ので長期に渡る生活が低気圧に対して対抗するように身体を調整する(順化と、いう現象だったと思う)ようなメカニズムが分子レベルでも働いているとするなら、そして、その様なメカニズムが細胞内のデータベースであるDNAに対して書き込みを行なうメカニズムと連動しているのなら
勿論、以上の事柄は素人である私がTVプログラムでかいま見た専門家の方々の真面目な研究に刺激されて、勝手に想像の翼を広げ現実から乖離した空想を繰り広げて来たに過ぎない。
環境が生物を作り替えて行く、というのは、一応正しいを認められるコトではないだろうか? 進化論について語った本をひもとくと、石炭を主力燃料とする19世紀のイギリスの工業都市の近くの森の樹々の肌の色が黒くなるにつれて羽の黒い蛾が白い羽のがに比べて多くなった、公害問題が解決するにつれて白い羽の蛾の勢力がまたもり返して来たことが書かれてような気がする。その理由については、樹の肌の色とのコントラストにより目立つ蛾の方が捕食され個体数が減り、それに伴い、次の世代の数の差が広がって行く。と、述べられていたが、そのメカニズムに加えて、環境に沿って生物が自らを緩やかに変化させていくとしたなら、環境汚染の影響というものは、我々が気がつかないより大きな側面をもっているのかも知れない。
この文章を書いている最中に考えていたことは、アトミックソルジャー・広島・長崎・スリーマイル島・チェルノブイリ・そして、多分これからも起こるであろう異常なレベルの放射能を浴びた方々のことだ。我々が原子力を使い始めてから極めて短い時間しか経ってはいない。多分、我々が学ぶべき事柄は、これからも決して無くなることは無いだろう。そして、原子力だけではなく、様々な物質(新しい物質というだけではなく、知られている物質の濃度とか摂取する期間とか、世代を経るにつれての影響とか)についても、そしてよく知られている物質・我々を含む生態系についても、我々が完璧な知識とモラルをもつ日が来ることはないだろう、ということだった。
以上の文章はあくまでも、素人の門外漢である私が、あるTVのプログラムに刺激されて、勝手に、気分任せで、想像の翼を広げ現実から剥離した空想を展開したに過ぎない。多分、専門家の方々は、一笑にふされることだろうと思われることを、再び明記しておく。
終り
()注釈のカラー化は、今回のアップロードの際に付加した。
(エッセイ 環境汚染に関する)
発生の問題 7/1/03 1:47:52 PM JMT 近藤敏郎
DNAが、最初の生物なのかという問題。
(発生の問題)
書庫
(書庫)
updated:7/7/2005
1:28:43 AM JMT mail address changed.
Updated: 7/1/03 1:49:16 PM JMT
Updated: 10/7/03 8:30:13 AM JMT
Updated: 6/3/2004 1:45:48 PM JMT
<End of contents. >